

福山は広島県の東端にあり、南に瀬戸内海を臨みます。
ちょうど瀬戸内海の中央ぐらいに位置し、温暖な気候の地。
(ちなみに、福山の南端にある“鞆の浦”は、スタジオジブリ作品「崖の上のポニョ」のモデルとなった地です。宮崎駿監督が鞆の浦に長期滞在し、その構想を練ったといいます。)
創業時のメンバーは、雑木林を切り拓き、土地を整え、養豚場を開設したのです。

造成時集合写真

牧場造成
その頃は、ちょうど高度経済成長期の真っ只中。
お肉に対する需要も高く、次から次へと仔豚を買い入れ育てていきました。
そして、豚に限らず、牛や鶏の肥育にも手を広げていき、順調に伸びていっていました。

ところが、いつしか「このままでいいのだろうか?本当に美味しいと言ってもらえるものができているのだろうか?」と思うようになったのです。

そこでまず、仔豚を買い入れるのではなく、繁殖から手掛けることにしました。
そうすることで、豚肉の品質の安定がはかれるからです。
また、初心に戻り、牛や鶏の肥育をやめることにしました。
豚一本に絞り、そこに心血を注ぎこんで、自信を持って提供できる豚肉の生産に取り組みました。
まずは、豚の飼育環境です。
通常の養豚施設に比べ、1頭当たりの居住スペースを2,3倍広いものにしました。
豚が自由に走り回ることができ、放牧的に飼育するためです。

そして、その床は、間伐材のウッドチップを1m程敷き詰めたバイオベッド。
ウッドチップの中にいる微生物の働きによって、豚の排泄物が自然分解されるのです。
その効果で、臭いがあまりしなくなりました。
こうして、デリケートな生き物である豚にとって、広く、臭いが少ない環境で、
ストレスなく育てることができるようになったのです。
もちろんエサにもこだわりました。
通常、豚の飼料はトウモロコシ主体の配合飼料と呼ばれるもの。
その一部を替えて「パンの耳」を与えたこともありました。
パンを与えることで、お肉にほどよく脂がのるのです。
霜降りの牛肉ってありますが、それと同じように“霜降り”の豚肉になりました。
水にもこだわりました。
強力な磁気を通過させた水を与えたのです。
クラスター(粒子)の小さな水に加工したアルカリイオン水は、体に吸収されやすいからです。
このことによって、豚の毛並みがよくなり、健康になりました。

でも、もっともっと美味しい豚肉にするためにはどうしたらいいのか?
研究を重ねる日が続くなか、鹿児島の焼酎を造っている会社が、
麹(こうじ)菌を使って発酵飼料を造っているという話を聞きました。
焼酎を製造する際に用いられる“黒麹菌”です。
その黒麹菌と、ご飯やパン、野菜などと水を、ある配合率で混ぜ、
一定温度で一晩発酵させると、まるで甘酒のような飼料ができるのです。

人間だって、発酵食品が健康にいいといいます。
豚だってきっと同じ。元気になるに違いない!
資金を投じ製造施設を造り、その甘酒のような液状の飼料をつくり、与えました。

みんな、美味しそうに甘酒のような飼料を食べています。
それだけではありません。
そのお肉の脂は、それまで以上に、あっさりしながら甘みと旨みが増したのです。
それに加え、脂の融点が低くなり、口の中で溶けやすく、柔らかいお肉となったのです。
コレステロールとして体に蓄積しやすい脂肪ではなく、旨みをたっぷり含んだオレイン酸やリノール酸が多く含まれた脂肪に変わりました。
大成功です!
もともと人間が食べるものを原料にしたものです。栄養価も高い!
そのうえ、発酵させることでできた、クエン酸や微生物がつくる消化酵素が豚を健康にしたのです。
ストレスなく健康に育った豚のお肉は、ほんのりサクラ色に染まり、
お肉本来の旨味が凝縮されているのです。
こうして、瀬戸牧場の豚が出来上がりました。
でも、これだけではありません。
さらなるこだわりによって『瀬戸のもち豚 せと姫』ができるのです。

オス豚のお肉は、メス豚に比べ、肉が固く、独特のいやな臭いがあります。
そのため、オス豚は生まれてすぐに去勢します。
それでも、どうしてもそのお肉には獣臭が残ってしまいます。
獣臭があると、食べたときに、ほんの少しではありますが、臭みが残ってしまいます。
だから、『瀬戸のもち豚 せと姫』はメス豚だけなのです。
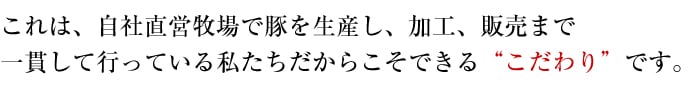
これら、ひとつひとつの“こだわり”の積み重ねで出来上がった『瀬戸のもち豚 せと姫』。
まだ、これで完成というわけではありません。
笑顔で食べていただける美味しさを提供すること。
それが、私たちの望みです。

それを叶えるために、より美味しいお肉になるよう、
今日も日々研究を積み重ねています。

